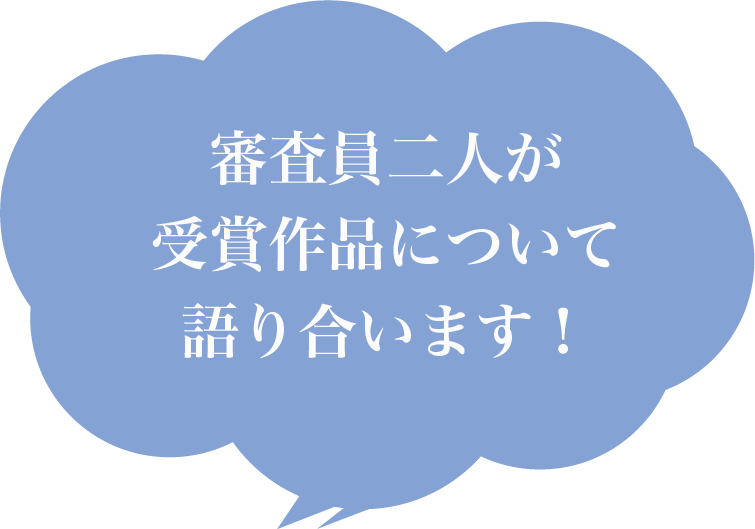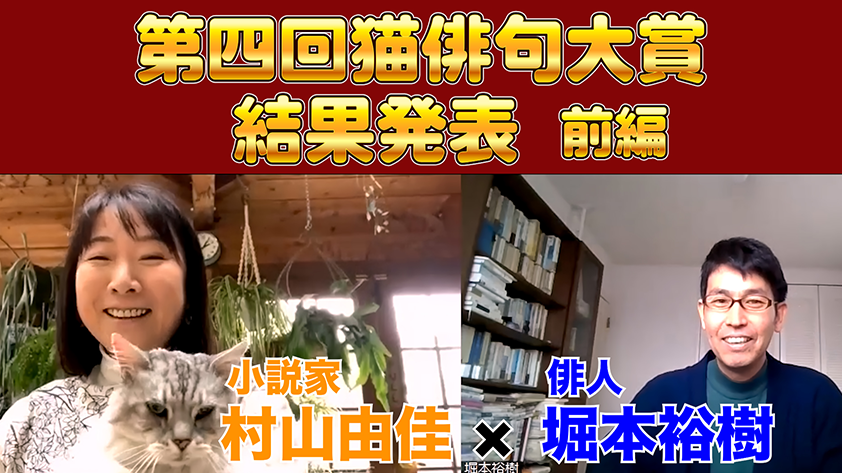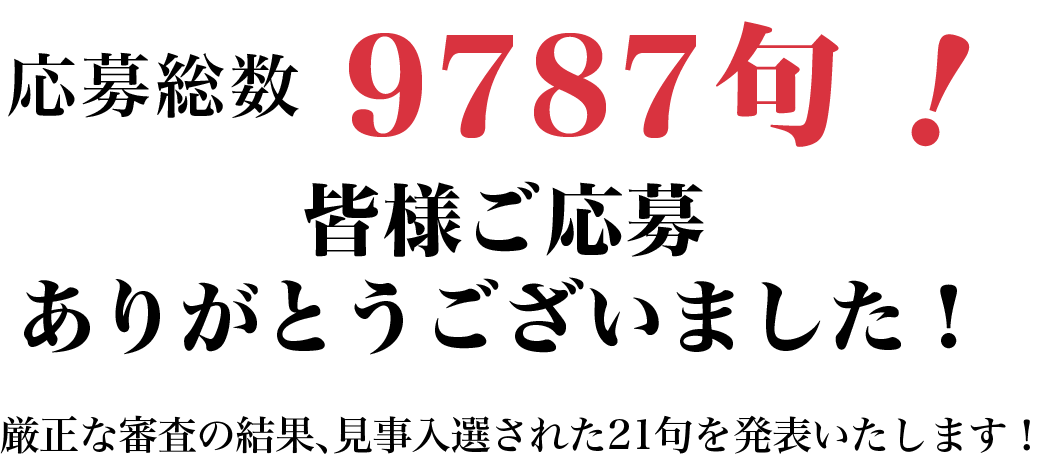

サスケくん
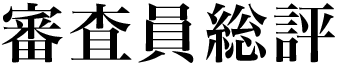

撮影 庄司直人
第四回猫俳句大賞にご応募してくださった皆さん、ありがとうございました。今回もさまざまな猫の表情に出会うことができました。そして人間と猫とのいろいろな関わり方や交流の場面に俳句を通して触れました。それこそ、これだけ猫の句をたくさん読んでいると、だんだん猫が人間のように見えてくるから不思議です。実際猫は猫なんだろうけれど、なんだかほんとに不思議ですね。
堀本裕樹(俳人)

猫の可愛さや仕草を描写するだけでなく、そこから人の生活や、生きることの喜びと哀しみが垣間見える秀句がたくさん寄せられたことに驚きました。私自身は不調法で読ませて頂くいっぽうですが、あえて皆まで言わずにいることによって余韻が味わいを深めるような作品に心惹かれます。
たったの十七文字が孕む無限。俳句って、いいですねえ。
村山由佳(小説家)
老猫の
まばたきふかき
春の宵
青木りんどう

老猫の今まで辿ってきた生き様が「まばたきふかき」の一つの動作に象徴されているようだ。そして「春の宵」の季語から「春宵一刻値千金」の諺が連想される。春の夜は趣深く、そのひと時は千金の価値があるという意味だが、長く生きてきた猫が、この春のひと時を慈しんでいるような「ふかきまばたき」に見えるのだ。静かに際立つ老猫の存在感。
(堀本裕樹)
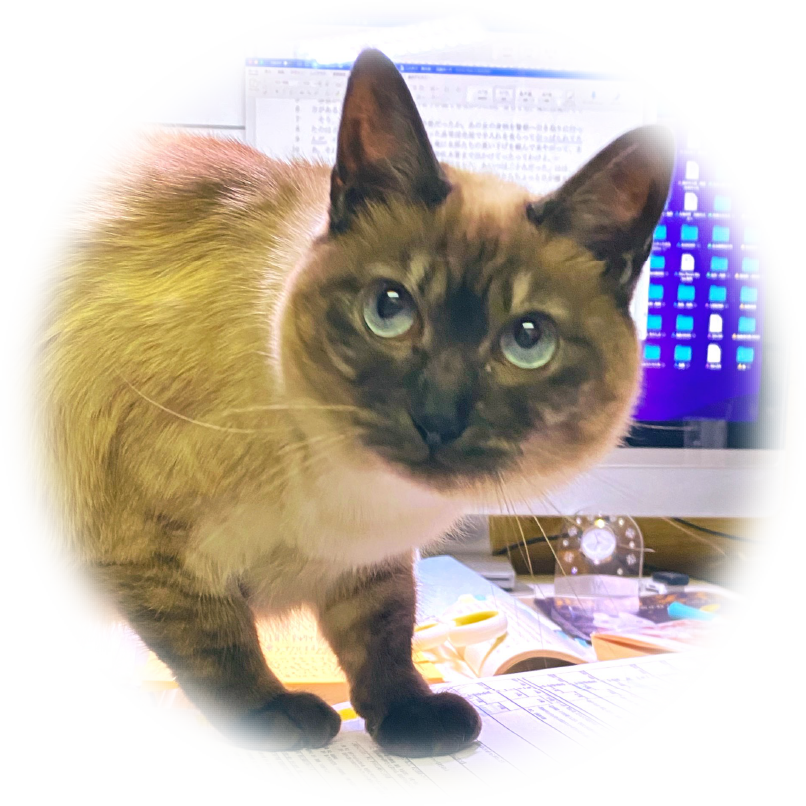
お絹ちゃん
猫俳句大賞受賞者には
副賞10万円を進呈いたします!
頑なに
食わず癒えたり
冬の猫
あいむ李景

運命を受け容れつつ、死の瞬間までひたむきに生きようとする命。私自身、愛猫の三毛を闘病の末に看取った時、当の彼女に死を怖れる様子がないことに救われたのを思いだします。この句からも、治るために何が必要かを本能でわかっている、そんな生きものの底力と凄みを感じました。頑固な猫を見守るしかなかった作者の安堵と、命への感嘆も。
(村山由佳)
猫俳句準賞受賞者には
副賞5万円を進呈いたします

銀次くん
- 調弦のごと猫のひげ震へ秋石井一草
- まるで楽器の弦のごとく並んだ立派なひげが、秋特有の澄んだ空気、斜めに射す金色の陽射しの中でびりりと震える。冒頭から「調弦のごと」と切りだすことで力強さが加わり、実際には聞こえない音や振動までも感じられるようです。最後の「秋」の言い切りがまたいいですね。張りつめた弦のように一本筋の通った潔い句です。 (村山由佳)
- 声消えて成就したるか猫の恋ヤンクマークパパ
- 春の季語「猫の恋」を用いた句は候補作の中にも沢山あり、ほとんどは呼び交わす声の大きさ、恋の激しさを表現したものでしたが、この句だけはその声がふっと消えた後の余韻に感動の中心があって、それが新鮮でした。暗がりでじっと動かない二匹の猫の姿が、描かれていないのに浮かんできます。 (村山由佳)
- 抱く猫は黒こそ良けれ春炬燵中山裕江
- 「黒こそ良けれ」と言い切るくらいですから作者の愛猫は黒猫なのでしょう。その光景を思い浮かべればなるほどと納得させられるのですが、たとえばそれを「白こそ良けれ」「縞こそ」「シャムこそ」と置き換えても何の違和感もなくて、要するに、愛したこの子こそがいちばん、という愛情の吐露と読みました。ますます納得です。 (村山由佳)
- 離るるといふいたはりよ猫の夫川又 夕
- 人間界では、恋した二人が末永く一緒にいられるのが幸福とされがちですし、子育てにしても夫が責任を分担するのが当然のこととなりつつあります。引き比べて猫の牡は交わった後すぐに牝を離れ、それ以上は干渉しない。そこにあえて「いたはり」を見出そうとするところに、ひとりで凜と立つ作者の矜恃を感じます。 (村山由佳)
- 熟れ柿や猫一匹を飼ふ重みとりゆふ
- 人ひとり猫一匹で暮らしていた頃は外出のたび、自分に何かあったら部屋で待つ猫はどうなるのだろうと怖くなったものでした。垂れ下がった枝の先に残る熟柿、その今にも皮が爆ぜて破れそうなほどの柔らかさと重み。見上げながらふと胸に浮かぶ、ひとつの命を守り抜く責任と哀しみ。秋空の蒼さまで浮かぶようですね。 (村山由佳)
- 猫に飯くらいは出せる春の風邪ルーキー
- 病にまつわる句も多くあってどれも切実でしたが、この句には思わず微笑してしまうような軽みがありました。ようやく寒さのゆるんだ春先にうっかりひいてしまった風邪の程度が、「猫に飯くらいは出せる」の言葉に過不足なく表現されていて秀逸。猫のほうも飼い主の体調をちゃんと見極めているようです。 (村山由佳)
- 猫にのみ告げる過ち冬桜円山なのめ
- 人には言えない秘密や失敗を、猫に打ち明ける。誰もが経験することと思います。ただ、この句からはほんのりと倫ならぬ恋の匂いがするようです。しかも「冬桜」。春の桜ほど爛漫と咲いて散るわけでもなければ、また冬薔薇のように主張することもない「過ち」。それでも猫にだけは告げずにいられなかったのですね。 (村山由佳)
- 鈴生りの子猫にひとつづつ乳首真篠みどり
- 猫の子育てを間近に見たことがある人なら頷かずにいられない句です。それぞれにマイ乳首が決まっていて、押し合いへし合いしながら懸命に吸いつき揉みしだく、あの旺盛な生命力の愛おしさ。見つめる作者の表情まで想像できます。特別な言葉はつかっていないのに、特別な光景が目に見えるのがいい。 (村山由佳)
- お師さんに猫の爪あと花の宴露草うづら
- お稽古事は茶道? 三味線だったらなお面白い。ともあれ、いつも厳しいお師匠さんの、手の甲あたりに赤い傷が三本ほど。恋に逸る猫のお出かけを邪魔して引っかかれたのでしょうか。憧れのひとの、ふだんは謎に包まれた生活がふと垣間見える瞬間、なぜかちょっと色っぽくてどきどきしますね。 (村山由佳)
- 猫ごきげんぢやんごきぶりばらばらぢやん彼方ひらく
- 一読、ふきだしました。自由律というほどはみ出してもいないのに、とても自由な風を感じます。「猫」以外はすべて平仮名で、じっと睨んでいると文字の様子から「ばらばら」の光景が浮かんでくるのが困りもの。飼い主にとっては絶叫モノの不幸でも、猫がごきげんならすべてはゆるされるぢやん。 (村山由佳)
- 秋の夜や動画の猫を撫でてみる船橋昭彦
- 猫を飼っていない人か、それとも亡くした猫の動画だろうか。秋の夜長の寂しさに猫の動画を見ているのだろう。つい手を伸ばして画面の猫に触れてみたのだ。だが、当然そこに猫の温かみはない。平板な画面に映る猫に余計に愛しさが募る。季語は「秋の夜」で秋。 (堀本裕樹)
- 猫の耳動いて一葉落ちにけり鈴木優二
- 猫の耳が動いたからといって桐の一葉が落ちたわけではない。桐の葉が落ちることを素早く察知して猫の耳が動いたのかもしれない。猫の耳が繊細に動く様子と、秋の訪れを知らせる桐の葉が落ちる光景とが、不思議に響き合う一句である。季語は「一葉落つ」で秋。(堀本裕樹)
- 渡り漁夫何もねえぞと茶虎撫づ佐藤直哉
- 「渡り漁夫」とは、鰊漁がはじまる春先に網元に雇われて北海道へ渡る漁師のこと。その漁師に甘えるように、茶虎の猫がすり寄っていったのだ。「何もねえぞ」の漁夫の無骨な言葉に優しさを感じる。ほんとうは猫に何かあげたいのだろう。季語は「渡り漁夫」で春。 (堀本裕樹)
- 雪しまき子等駆けつける猫のオペ梶 政幸
- 「雪しまき」とは、雪が激しく風が吹き荒れること。そんな荒天の折、猫の手術が行われる。猫の一大事に、子ども達も駆けつけて手術の成功に祈りを捧げる。どうか無事に手術がすみますように。雪まみれになって来る子等の情景が見える。季語は「雪しまき」で冬。 (堀本裕樹)
- 花の雨猫の棺を作る父井上右彩
- 桜に雨が降り注いでいる風景のなか、亡くなった猫の棺を父が黙々と作っている。猫の棺だから大きなものではない。小さな棺だけに余計に切ない。父は涙を見せずに作業しているが、代わりに天が泣き、桜が散って泣いているように見える。季語は「花の雨」で春。 (堀本裕樹)
- 内見の話題は子猫一辺倒恵勇
- 新しい家に引っ越す前に内見をしている。子猫を飼っているので、ペット可の物件だ。不動産屋のスタッフとの話題は、子猫のことばかり。それともまだ住んでいる内見先の子猫のことかもしれない。どちらにしろ、物件の要素より子猫が第一。季語は「子猫」で春。(堀本裕樹)
- すれ違ふ白猫の背にかなぶんぶんくま鶉
- 道端で白猫とすれ違ったのだろう。その猫の背に「かなぶんぶん」がしがみついている。一見、白猫のアクセサリーのようにも見える黄金虫だが、虫の側からすると、なんだか必死のような感じもする。二つの生き物の取り合わせの妙。季語は「かなぶんぶん」で夏。 (堀本裕樹)
- 猫抱いて心臓重ねあう小春益木うから
- なぜ猫を抱いているのか。何気なく抱いたのか。何かを猫に伝えたくて抱いたのか。そこは想像するしかないが、「心臓重ねあう」という行為に猫と人との親密な関係性が見える。お互いの心臓の音が響き合い、生きていることを実感する小春日和。季語は「小春」で冬。 (堀本裕樹)
- 跳躍の猫の一瞬月に入る彼方ひらく
- 月夜に猫がジャンプを見せた。どこか高いところからの跳躍だろう。そのとき、遥かな月と一瞬猫の姿態とが重なったのだ。遠近法を用いながら、猫と月とを一体化させた描写がいい。「月に入る」の措辞で、月の菟が瞬間猫に取って代わったのだ。季語は「月」で秋。(堀本裕樹)

佳作の皆様には副賞として
クオカード1000円を
進呈いたします!

著作権・個人情報について
応募作品の著作権はすべて株式会社アドライフに帰属します。
応募に際して取得した個人情報は、受賞のご連絡や賞品発送等の「猫俳句大賞」の運営目的においてのみ利用し、それ以外の目的で利用することはありません。
※まどけいさんの作品、「ぽつねんと花見る猫のよき姿」につきまして、類似した先行
句があることがわかり、協議の結果、佳作を取り消しとさせていただきました。